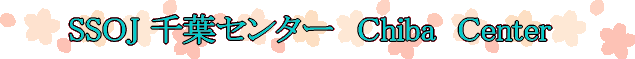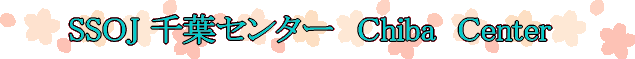2024年4月の御言葉
もっとも容易なのは、あらゆる行動を神に捧げることです。
「神よ、あなたの恩寵により、私はこれをすることができます。ですから、私はこれをあなたに捧げます」
と言いなさい。 けれども、口先だけのただの言葉で終わらせてはなりません。話されていることによって、心が変容しなければなりません。
[人生はゲーム、プレイしなさい! p.108 より]
4月の感想
2024年3月の御言葉
セヴァダルの責任はひじょうに重い。責任感を持ってメンバーは行動しなくてはいけない。
そしてこのメンバーを通し、全人類を「私」から「わたしたち」にする精神的規律に従うよう導いていかなくてはならない。これがセヴァダルが重要である理由なのだ。人は自分の内面の重要性を深く掘り下げてみない限り、この点には気づかないものだ。
仕事の全てを崇拝へと昇華していかなくてはならない。一生涯この見地に基づいて生きていく努力をしなくてはならない。そうしてこそ、あなたはこの組織の一員であると胸を張っていうことができる。
[ヴィジョン.オブ.サイ p.308 より]
3月の感想
2024年2月の御言葉
よく聞きなさい。目覚めたら、「主」に与えられた役を演じるために舞台にあがったのだと思いなさい。上手に演じて「主」の称賛をえられるようにと、祈りなさい。
夜、眠りにつくときには、舞台を終えて楽屋に入ったのだと思いなさい。でもあなたはまだ衣装を着けている。
おそらくまだ役は終わっていないので、衣装を脱ぐことはできない。翌朝には、また出番があるからかもしれない。
だが、心配することはない。「主」の裁量にすっかり身を任せればよい。「主」が承知している。「主」が「戯曲」を書いたのだから、幕切れも劇の進行もすべて「主」が知っている。あなたはただ役を演じて、舞台を降りればよい。
[ヴィジョン.オブ.サイ p.152 より]
「神」を愛しなさい。ただし、「神」を愛すことさえ「神」から授けられたものなのだ。われわれは与えられた「愛」を「彼」に返さなければならない。
[ヴィジョン.オブ.サイ p.181 より]
2月の感想
日々の憂いや家族も含む人間関係等、思い通りにいかないことや酷い状況にある時、私たちは皆役を演じている!を念頭に、一瞬は例え爆発したとしても、直ぐに気持ちを収めることができる助けになりました。
私同様、他の人も役割があり演じて居るのですから。そして同じところで引っかかる感情を、浄化せざるを得ないことにも気づいています。
今のところは少しずつでも、大いなる助けになっている、、に留まっているというところですが。 追記の、『神を愛すことさえ神から授かったもの』私たちにとって愛することは当たり前(出来ても出来なくても)で、考えたこともありませんでしたが、愛を知ること、知らずに生きることも神の恩寵だと知り、身震いするほどの驚きがありました。近しい関係に、愛とは程遠い方が居て、いったいどんな縁で繋がったのか、いつまで続くのか、どんな心になれば浄化されるのか、全く途方にくれてしまうことがあります。ですが、その方にもお役目があり、全ては自分から発信している。と考えれば、心も少し落ち着きます。
その方の心にも、無償の愛が目覚めるよう祈ってみようと思います。 愛する心を授かったことは、なによりの恩寵なのだから、愛を広げなければなりませんね。
サイラム
2024年1月の御言葉
帰依の心、不屈の精神、そして平安といった富を手にする方法を、あえて他人に助言しようと試みる前に、まずあなた自身がそうした富を手に入れなさい。
バーラタ(インドの正式な国名)は、自分が教えることを実践することに注意を払わなかった大勢の教師たちのために、軽んじられ、無視されてきました。
わたしたちは、あなたたちがわたしのメッセージをこの国の人々、そして他の国の人々に伝えることに熱心なことを知っています。
覚えていますか?あなたたちにできる最善にして唯一功を奏する方法とは、それらのメッセージを自分たちの実生活に移すことです。
あなたたちの思いと言葉と行いには、わたしの教えがしみ込んでいなければなりません。 そうすれば、わたしの教えは労せずとも効果的に広まり、世界の様相は一変することでしょう。
[1008の宝石 今日の御言葉集1 p.149 より]
1月の感想
サイラム
御言葉の後半部分が気に入って、この御言葉を選びましたが、実際には前半部分に関する学びがありました。
この1ヶ月間、神の恩寵により、他人に(言葉で助言はしなくとも)こうすればいいのにと思うことが多々ありました。心の中で思うだけでも、助言したことになると思いますので、沢山助言してしまったことになると思います。その度に、1月の御言葉を思い出し、心改めました。
「したいことをするより、しなくてはならないことを好きになること」「神に全託すること」「常な助け決して傷つけないこと」など、その都度、自分を改めました。周りや世界が変わることを考えるより、まずは、自分がスワミの御教えを守ることが重要なのだと思うようになりました。
サイラム
1月の御ことばで、私は、「労せず」がこころに響いてました。家庭が、ストレスフルで、心配が絶えませんので、労せずに一変してくれたら、と思うわけです。
そして、思い言葉行いに、スワミの御教えがしみ込んでいないのは、自分が学生期(今の子供と同じ)にやってこなかったたからだと気づきました。そして、多分、ストレスフルな状態は、私の行い(思いも含めて)の結果なわけで、これまで、一般に学んできたことと関係ない次元のことだと思いました。
今の状態と関係なく、とにかく神を信じて、出来るだけ愛して、世俗的なお願いの祈りから、霊的な導きと、朝昼夜や空気や命など、忘れがちなことへの感謝の祈りに変えていって、そして、自分の行いを少しでも正していくことかなと思いました。
それで、どうなるかわかりませんが、結果も(期待も)お捧げして、無執着でいないとなぁ、と思います。もともと理想があったのですが、それが世俗的に縛るような気がするので、、。神への信愛を膨らませていけたらと思います。
|
2023年12月の御言葉
思想としての愛は、真理です。
行為としての愛は、ダルマです。
感情としての愛は、平安てす。
理解としての愛は、非暴力です。
[静寂 P64 より]
12月の感想
|
2023年11月の御言葉
私たち各人の世界で起こることは、偶然でも、たまたまでも、不運でもなく、自分自身の思考や行動の結果なのですから、私たちはどうすれば安全で安心していられるのかは明らかです。私たちの唯一の安全は、軍隊や警察、警報機システム、武器、自衛の訓練、より良質な鍵やその同類のものにあるのではなく、むしろ、私たちの思考と思考から発する行動が優しくて慈悲深いことを確実にすることにあるのです。もし、あなたが、「ラヴ オール、サーヴ オール / すべてを愛し、すべてに奉仕する」、「ヘルプ エヴァー、ハート ネヴァー / つねに助け、決して傷つけない」ことを実践するなら、どのような害悪もあなたに起こらないでしょう。精神(マインド)を適切な状態に保ちさえすれば、悪い事は何も私たちに起こり得ません。
[思考の力 P103 より]
11月の感想
世界に起こる敵対的な思考、行動は他人事ではなく、自分が日々他人に対する批難も思考のミサイルとして相手を攻撃していると思い改めるようにしました。
思考のミサイルを撃ち込まない、よりは常に感謝する事を実行しました。
思うだけでなく、些細なことでもなるべく「ありがとうございます」と口にするようにしました。
結果、悲観的・否定的・攻撃的な考えが減ったというよりは、いかに感謝すべき事が日常に溢れているかの気づきでした。
|
2023年10月の御言葉
起こることは何であれ、神の意志によるものだという信念を持ちなさい。現代の世界では、自分の不幸をすべて他の人々のせいにして、幸福なときには自分自身を称賛することが日常茶飯事です。これは正しくありません。すべては神の贈り物であり、起こることは何であれ自分にとって良い事であるという考えを身につけなさい。幸福と悲しみ、利益と損失は、すべて過ぎ行く雲のようなものです!
[シュリ・サティヤ・サイ・ババ2006年講話集 p.230 より]
10月の感想
|
2023年9月の御言葉
五感を携えてこの物質的な世界で活動している時、悪い思考に悩まされるのは自然なことです。
人間には欲望(カーマ)、怒り(クローダ)、貪欲(ローバ)、愛執(モーハ)、高慢(マダ)、嫉妬(マーツアルヤ)という形をとった六つの敵がいます。
[真理のしずく P34 より]
9月の感想
|
2023年8月の御言葉
金槌で20回叩いても石を割ることはできないかもしれませんが、21回目には割れるかもしれません。これは、最初に20回叩いたことが無意味であったということでしょうか?いえいえ!1回ごとの打撃がそれぞれの役割を果たし、最終的な成功に貢献したのです。最後に現れた結果は21回全ての累積効果です!同様に、あなたの心は、内面でも外面でも、世俗と悪戦苦闘しています。言うまでもありませんが、常にあなたが勝つわけではありません。しかし、善良な仕事に没頭し、心を神への愛で満たすことによって、あなたは永続する至福に到達することができます。その愛を人生のあらゆる瞬間に注ぎなさい。そうすれば、邪悪な傾向が道を妨げようと挑んでくることはありません。常に心が神と共にあるならば、あなたは自然と善行だけに引き寄せられるでしょう
[プレーマ ヴァーヒニー P66 より]
8月の感想
|
2023年7月の御言葉
エゴをなだめる欲望のない、他者の幸福だけを考えたセヴァ(奉仕)を通じて、意識を浄化し、アートマンを顕現させることができます。
(自分が周囲から認められたいためにセヴァをする方がいらっしゃいます。神なるお方は、誰がどこで何をどのようにしているのか全てご存知です。もちろん、どのような気持ちでしているのかもです。故に、全く他者がいらっしゃらない所でセヴァ(陰徳)をしても、恩寵に値するのです。他者の評価を求めるより、無心で好意のみで行うセヴァを神なるお方はお喜びになるようです。くれぐれも、セヴァをする時は無心で好意のみを心掛けてください。それが本当に無償の愛ということです。また、無心であっても対象の方、対象のものに対しては、細心の注意を持って接しましょう。)
[Sathya Sai Speaks Vol.13 C9 より]
7月の感想
|
2023年6月の御言葉
目が与えられているからといって、すべてを見る必要はありません。よいものだけを見るようにしなさい。
他の人々の批判や不必要なものを耳に入れてはなりません。他者の批判を聞いたり悪いものを見ることは、大きな罪です。 悪を見たときのみに悪が身につくのです。私たちは、よい言葉を聴こうとする代わりに、悪い話に耳を傾けています。
スールダースは盲目でした。しかしスールダースは、絶えずクリシュナ神の御名を唱えていました。それゆえクリシュナ神は、スールダースにダルシャンと人生の成就を与えました。
なぜ神はあなたに舌を与えたのでしょうか? 一切合切すべての味を楽しむため、他の人々の悪口を言うためでしょうか? いいえ、そうではありません。舌は神の栄光を歌うために与えられました。
シュラーヴァナム(神の栄光を聴くこと)、キールタナム(神の栄光を歌うこと)、ヴィシュヌスマラナム(神を憶念すること)、パーダセーヴァナム(神の蓮華の御足に奉仕すること)、
ヴァンダナム(神を崇敬すること)、アルチャナム(神仏の像を礼拝すること)、ダースヤム(神の召し使いとして奉仕すること)、スネーハム(神の親しい友となること)、アートマニヴェーダナム(真我なる神に全託すること)
――人間はこれらの礼拝の方法(バクティ マールガ、信愛の道)を実践することによって、神を実現することができます。
[2007年1月27日の御講話より]
6月の感想
|
2023年5月の御言葉
「わたし」に到達したいなら、「愛」をつちかいなさい。
憎悪、嫉妬、怒り、皮肉、虚偽を捨てなさい。
わたしはあなた方に、学者になること、あるいはジャパ(神の御名をくりかえし唱えること)とディヤーナ(冥想に熟練した隠遁者や苦行者になってもらうことを要求しているのではありません。
あなたのハートに霊的愛が満ちあふれているかどうか、それをわたしは調べるのです。
[黄金の宇宙卵 P78より]
5月の感想
|
2023年4月の御言葉
あなたは他人のことを心配する必要はありません。自分自身のことだけ心配しなさい。
それで十分です。あなたが整えば他の人も整います。
[真理のしずく P96より]
4月の感想
|
2023年3月の御言葉
あらゆる霊性修行の目的は、心を滅することです。いつの日か、21回目の打撃のように、一つの善行が心を滅することに成功するでしょう。過去に行われた善行のすべてが、この勝利に貢献したのです。ささやかな一つひとつの行為すべてが大切です。無駄になる善行などありません。
[プレ-マヴァーヒニー P.67より]
3月の感想
サイラム "ささやかな一つひとつの行為すべてが大切です。"を心に留め、日々を送りました。スワミの学生がスワミのご様子をいつも気にしながら、ちょっとしたことも見落とさずに、すぐに気づいてサッと行動されていたのを思い出して、見習ってセヴァを行いました。今までは、自分がしていることが終わってからセヴァをすることがありましたが、その頃には用済みになっていることも度々ありました。今月は、ちょっとしたことでもすぐに行動に移しましたので、相手に喜ばれ、良かったです。
サイラム
|
2023年2月の御言葉
真の自己とは、裁かず、評価せず、比較せず、非難せず、分離せず、いかなる保証をも求めず、自分自身すら求めない自己のことです。
それは自らを完全に放棄した自己です。
しかもなお、不思議かつ神秘的なことに、それは、決してこれまでそうあり続けてきた以上に完全ではなく、それ以上に真実であることも、それ以上にそれ自身であることもないのです。
これが真の自己(真我)です。
[プレ-マダ-ラ P.32より]
2月の感想
|
2023年1月の御言葉
一番良いのは、各人が割り当てられた義務を果たすことです。それは最高のダルマです。
[サイの理想 P.270より]
1月の感想
割り当てられた義務とは、仕事や家庭内でのやるべき事は勿論、目の前の事象に対しての気持ちの持ち方を指しているのではとの思いで御言葉を解釈しました。
つまり、嫌な目にあっても怒りを抑える事や、周りに同調して特定の人を非難しないなど実に当たり前の事です。
割り当てられた義務とは日常に起こる差些細な事に対して如何にスワミを思って対処出来るかだと思いました。
ただ、些細な事だからこそ自分を律して守り抜くのは根気がいり難しいことです。
また仕事などの義務も如何に誠実に行えるかが問われていると思いました。
|
2022年12月の御言葉
「《エゴ》こそがあらゆる困難を引き起こす根源。
エゴを立ち去らせてしまえば私たちの全ての困難は消えゆく。」
[プレーマダーラ P.10より]
12月の感想
|
2022年11月の御言葉
「あらゆるとろこでサイの存在を感じるようでなくてはなりません。サイの理想の生き方を理解し身に着けた時に、初めて、サイの恩寵が皆様の上に注がれるのです。」
[プレーマダーラ P.21より]
11月の感想
|
2022年10月の御言葉
「劇の中の役者として、すべての仕事をしなさい。役者を自分自身と同一視することや、自分の個性や役柄に執着することがあってはなりません。すべは単なる芝居にすぎず、神があなたに役割を与えているのだということを心に留めておきなさい。自分の役を上手に演じなさい。そのとき、すべての義務が終了します。神が芝居を作り、それを楽しんでいるのです。」
[サイの理想 P.262より]
10月の感想
|
2022年9月の御言葉
「思いと言葉と行動を一致させなさい。」
[参照文献多数]
9月の感想
|
2022年8月の御言葉
昨今、人々は神聖な聖典の字句を読んでいても、信仰をもっていません。
ある学生が師に要求しました。
「先生!私はもう二十年間も『バガヴァッドギーター』を読んできました。私は七百の詩節をすべて暗記しています。ですが、その努力から何一つ良い結果を得ることはありませんでした。成果を手に入れることのできるマントラを伝授してください」
師は大声で叫びました。
「出ていけ、この愚か者よ!おまえはずっと、神ご自身の教えであるギーターを読んできた。おまえは神の言葉を信用しておらんくせに意味不明なマントラは信用するというのか?真心を込めてギーターの教えに従っていれば、なぜマントラなど必要であろう?神に信用を置かぬ者にマントラが何の役に立つのか?」
[1995年夏季講習 シュリーマド・バーガヴァタム P.180より]
8月の感想
|
2022年7月の御言葉
人類同胞への信愛には神への信愛が含まれます。神への信愛は人類同胞への信愛です。信愛が無ければ、根無し草のようなものです。乾燥しすぐにしぼんでしまいます。この信愛とは、内面からの促しによってものを言わせたり、行為や行動をさせたりするときに「私」「私」「私」と言わせている内面の神を信じることです。信愛という栄養によって愛と勇気、満足、そして喜びが増大します。子供たちはこの内なる「私」に容易に気づくことができます。
[サティアサイが語る子育て P.22より]
7月の感想
千葉センターの記念祭の折に、
「スワミの体験談を語ることが神を讃えることである」
と、教わりました。帰依して18年目にて初めて「神を讃える」ことをどのように実践すれば良いかを理解できて目からうろこが落ちた思いでした。
7月の御言葉に
「神への信愛とは人類同胞への信愛」という言葉がありますが、過去において同様な御言葉を読んでいても自分の中には理解として定着していませんでした。
今回、初めて「神へ信愛を捧げる、或いは神を愛する」ことをどのように実践すればよいか理解できた気がします。
今まではスワミの御教えを一から十まで実践する努力をすることが神を愛することと思っていましたが、今では人類同胞へ信愛を保つことを最重要視しています。
同じ毎日のお祈りにおいても心のおき方一つで異なる効果が出てきているように思います。
|
2022年6月の御言葉
悪い行為は決して善をもたらさない
良い行為は決して悪を生みださない
ニームの種は、マンゴーの実を結ぶことはなく、マンゴーの種がニームの実を結ぶこともない
6月の感想
私はこの御言葉が大好きで、いつも胸に置いています。
御言葉のお話しがあったときには、私にはこれしかないと思いました。
シンプルで美しい言葉の羅列、万人に分かりやすく、人は平等なのだとわかるのです。
自分のしたことは、良いことも悪いことも自分に返ってくる。
だから、人を責めることはできないのです。
------------------------------------------
泣いても笑っても怒っても、全ては自分の責任
------------------------------------------
真に府に落ちれば、自立に向かって動き出すと思うのです。
------------------------------------------
全ては自分の責任、自分から出たこと、と戒めて、気持ちを良いほうに向けるよう試行錯誤しています。
------------------------------------------
自分のした良いことも悪いこともすべて自分にかえってくる。
極力良いことのみをと思いますが、私の場合は思いに特に注意をはらいました。悪いことの重さを思い、これからも日々を過ごしたいと思います。
------------------------------------------
日常の問題が気になり、瞑想に集中出来なかった日に、過去に蒔いた悪い種子の収穫時期を迎えただけなのだということに気づいた。過去の行いの結果、托鉢に行っても人々から石を投げられ日々血まみれになりながらもアングリマーラが、静かに、避けることもせずに耐えたように、平安な気持ちで耐えようと思った。
|
2022年5月の御言葉
「私」は肉体ではありません。あなたは、身体のことを、「私の」という言葉を付けて呼びます。それは私の身体であるとか、私の心、私の目、私の顔であると言います。それでは、その「私」とは誰でしょう? あなたが、私の顔と言うとき、あなたは、顔とは別の何者かではないのですか? これは私のハンカチです。これは私の花です。花は私から離れています。ハンカチは、私とは別物です。それでは、「私」とは誰でしょう? 私たちは、このようにして探求しなければなりません。これが識別です。私たちは、このようなやり方で、真剣に識別をしなくてはなりません。そうすれば、あなたは、「私」というものの真の姿を見るでしょう。
[真実の探求 P.74より]
5月の感想
途中経過の感想です。毎日の15分黙想は、全然出来てません。朝の光明瞑想など、何かのついでにしてます。感想は、ナガティブな感情に支配されそうなときに、「私は誰か?」の言葉を思い出すと効果がありそうです。祭壇の前ですると、もっと効果があるような気がしてます。さいらむです。
------------------------------------------
15分と時間を区切らずに、気がついた時に「who am I 」と自らに聞いていました。
最初の1週間くらいで聞いてから数秒ー10数秒位騒がしい心が止まって思考が停止するようになりました。
また思考が始まる前にナーマスマナラを実施すると集中して出来るようになりました。
年単位で継続して習慣化したいと思います。
------------------------------------------
ほぼ毎朝15分「Who am I?」を続けてみました。心はよく動き、その都度連れ戻して「Who am I?」と問うていました。この15分につきましては、特に何かが変わった感じはしません。
生活しているときに、ときどき「Who am I?」を思い出して、問いかけるようになりました。問いかけても、答えは出ませんが、これからも継続していきたいと思います。
------------------------------------------
最初は毎日15分していたのですが、途中でこれで良いのだろうかと行き詰まってしまいました。
そんな時に送ってくださった(誘導の仕方)がとてもありがたかったです。
途中経過ですが、15分間と日常生活の中でも(私)に注意をはらうようになりました。
ずっと続けていきたいと思います。
-----------------------------------------
全ては非現実になってしまい空虚のような空っぽになってしまいました。
言葉に出来ないまま日にちが過ぎてしまい遅くなりました。
|
2022年4月の御言葉
愛はいかに培えばよいでしょうか。まず、つねに他人の欠点は取るにたらぬことと考えなさい。つぎに、自分の欠点はどのように些細であろうとも大きく考え、悲しみ、悔い改めなさい。なにごとをなすときも、ひとりでしようと仲間としようと、つねに神が遍在であることを忘れてはなりません。絶えず神の全能を自覚していなさい。
[静寂 P.70より]
4月の感想
今現在、多大な苦しみ、悲しみの中におられる方々のことを考えますと、自分に起こる事など大したことではないと思っておりましたが、テストを受けているように大きな事が出てきました。ついつい心の片隅で相手を非難する思いが出てきてしまいました。
ですが、そのおかげでスワミに向き合う時間が前よりも増えました。
神の遍在、共におられることのありがたみを感じました。
まだまだ、常に心を神様に向けているということは難しいですが、そうなれるように努力したいと思います。
------------------------------------------
他人の欠点に目を向けたくなったとき、それは自分の反映であり、自分を整えることが大切なのだと思いました。自分の欠点、悪い行いは自分に返ってきますので、罪は怖いです。
|
2022年3月の御言葉
平安をもたらすには、愛と忍耐さえあれば十分です。しかし、単なる外側の見せ掛けのみに意識を集中してはなりません。愛と忍耐という美徳があなたの想いと言葉と行動を満たすようにしなさい。それは、世界平和を確立する道でもあるのです。
[至高の平安 P54より]
3月の感想
今回の戦争では悲しみ、日々の生活では怒りやイライラ、に支配されそうになってしまいます。
いかにして負の感情の支配から逃れるかは自分本位から相手のの立場からの視点が重要でした。
改めて2月の御言葉の重要性を感じる事になりました。
何度も「理解される事よりも理解する事を」の言葉が思い起こされる日々でした。
忍耐は相手に対してよりも気持ちが乱されそうになると負の感情に対し繰り返し「理解する事を」と自分に言い聞かせる事でした。
------------------------------------------
日々過ごしている中であまり忍耐を必要する場面が少ないように思っておりましたが、このみ言葉を頂いてまだまだ忍耐が足りていないことに気づきました。
愛の心で目で、物事を見るようにしなければと反省しました。
------------------------------------------
加齢とともに能力の低下が起こり、それに抗う気持ちが寛容さを失わせている現状においてこの御言葉はとても響いております。精進したいと思います。
------------------------------------------
愛と忍耐と言っても・・・何でこうなの?と思うことが沢山ありました。そういうときに、一見悪い状況に見えても実は自分にとって最も良い状況なのだ、と思うように心がけました。思い起こせば、自分もかつてはそのようなことをしていたな、などと思い出すこともあり、カルマ解消のチャンスということで忍耐することもありました。
------------------------------------------
今回の戦争では悲しみ、日々の生活では怒りやイライラ、に支配されそうになってしまいます。いかにして負の感情の支配から逃れるかは自分本位から相手のの立場からの視点が重要でした。改めて2月の御言葉の重要性を感じる事になりました。
------------------------------------------
何度も「理解される事よりも理解する事を」の言葉が思い起こされる日々でした。忍耐は相手に対してよりも気持ちが乱されそうになると負の感情に対し繰り返し「理解する事を」と自分に言い聞かせる事でした。
|
2022年2月の御言葉
社会は人々が集まってできています。社会においての、自発性と純粋な意図によって動機付けられた人間同士の協力が、セヴァ〔無私の奉仕〕の証(あかし)です。セヴァには根本的な特徴が2つあります。それは、相手を思いやる気持ちと、進んで犠牲を払うことです。
[1981年11月19日 セヴァダル大会における御講話より]
昨年より、認知症初期の母と1年の半分程を過ごすようにしました。
母の必要を満たし、母が心穏やかにすごせるように手助けをしようとの思いは重々ありますが、相手がどういう状態で、どう思っているかに想いを巡らせず、時に思いやりのないことを言ったりしてしまいます。
「相手の立場に立って考える」とはよく言われますし、そうしようとは思いますが、常にそうあるのは難しいなと思い、この度はこれに取り組むことにしました。
もちろん、この御言葉に対する思いでも良いですし、相手を思いやることから、進んで犠牲を払うという行動に移すまでにある色々な障害や、どうそれを乗り越えるかということや、それらに関するスワミの御言葉を紹介して下さっても良いです。
でも今回はその中で、何かをする時に「相手の立場に立って考える」ということはやってみてください。
そしてその、うまく行ったり行かなかったりの経験をメール等で分かち合い、より良く実践出来るようになりたいと思います。
2月の感想
私にとっては認知症の母との関係が主で、母が何度も同じことを聞いてきたり言ったりするときや、トンチンカンな受け答えをするときに、ある程度までは優しく答えられるのですが、段々ぞんざいに答えるようになってしまいます。
母にすれば、単にさっき聞いたことの答えや、聞いたこと言ったこと自体を覚えていないからそうしているだけだし、聞いたことを理解して答えた言葉が、私が言ったこととはズレていただけで、意図して変なことを言っているわけではないのに、なぜそのままに対応できないのだろうと考えたとき、母の現状をそのままには受け入れられずに、以前のようであってほしいという気持ちが「相手の立場に立つ」ことを妨げているのだと気付きました。
それは、認知症の症状を改善できるであろう方法を今の状況では十分に行えないことへの満たされない思いや、そもそも肉体のレベルでしか母を見ていないことが原因だと思いました。
身近な人ほど姿形への執着が強いのでなかなか難しいのですが、母のこの姿は魂がまとった一時的な衣に過ぎず、それは私と愛を分かち合うため、私が気付いていない私の色々な面を気づかせてくれるためにあるのだと思って接するように心がけました。
それでも優しく答えられないと思うときは一呼吸おくようにしたり、何度も何度も機会は与えられるので、少しずつ思いやりのないことを言わなくてもすむようになっています。
でもなぜ、相手を傷付けたいわけでもないのに、相手が嫌がるだろうと分かっていることをしてしまうのかは、より深く考えてみたいと思います。
そしてまた、そもそも相手の思っていること感じていることを分かることができるのだろうかという疑問がわきました。
色々なことに母がトンチンカンな受け答えをしたりするのでそう思うのと、どう感じているのかと思って聞いても “大丈夫” とか、こちらを安心させるようなことしか言ってくれないからそう思うのですが、これは認知症の研究をしていた医師が自分が認知症になり体験を綴った本を読んで、その不安や情けなさや混乱を知ることができました。
また、記憶力や論理的な思考力が衰えていっても感情は残っているので、プライドを傷つけるようなことは言ってはいけないとのことでした。
確かに母も “色んなことをすぐに忘れる” “何もできなくなった” と嘆いています。
また、誰かにされたことの不満を言うときに、何がいやなのかを知ることもできます。
完全には理解できなくても、相手に思いを巡らし、嫌がりそうなことはせず、喜びそうなこと、しなければいけないことを、相手が受け入れやすいように言ったりしたりすることが大切だと思いました。
それがどうだったかは、喜んだり戸惑ったりの表現から知ることができますし、スワミが気付かせてくださいます。
「最善を尽くして、結果は神に委ねる」だと思いました。
------------------------------------------
職場やセンターで、セヴァ(人の中におわす神への奉仕)をするときに、同僚や家庭(家族)を犠牲にしていたことに気づきました。周りの方々に皺寄せがいかないように、周りにも気を配りながら、セヴァに取り組むように心がけました。
|
2022年1月の御言葉
われわれを導き守る神の存在を確信せよ。感謝と共に神を思い起こせ。自分を浄化するために神に祈れ。全てを愛し全てに仕えよ。よい仲間とつきあえ。寺を訪ね、有徳な者を訪ねよ。
(Sathya Sai Speaks, Vol. IV, P3)
1月の感想
普段ほとんどないのですが、今月の前半に心がざわざわする出来事がありました。日頃神様に何かにつけ感謝しておりましたが、今回はどうしても出来事に感謝ができませんでした。
ですが、今月のみ言葉を何度も目にしてすべては自分にとって良いことであるということ、また自分のエゴに気がつき感謝することができました。
ありがとうございました。
------------------------------------------
今月の御言葉を私なりに次のように解釈して、実践に繋げます。参考になれば幸いです。
「自分の心を乱すような出来事が起こったとき、憤慨したり落ち込んだりせずに、
これは神の導きであり、自分にとって最も良いことが起きているのだと信じ、神に感謝し、全てを愛し全てに仕えなさい。
私(神)を仲間として常に思うならば、必ず私はあなたを守り、この出来事を無事に乗り越えさせます。神に出来ないことなどありません。
あなたの身体は寺院です。私はそこに住んでいます。扉を叩きなさい。私はあなたを待っています。ーババー」
最後にーババーと書きましたが、私の想像した御言葉ですので、肉体のスワミが話されたことではありませんので、ご注意ください。
------------------------------------------
1月2日の初夢に 太陽が出てきて中に天照大御神がおられました。
翌日の夢は自分のベッドに大型犬サイズのホワイトタイガー(西方守護の白虎かどうかまで覚えていません)が自分の足元で一緒に寝ていました。
少し怖かったのですが、良く懐いている感じでした。
年男なので縁起が良いと思いました。
日常生活においては、自分の進展は実感できていないのですが、記念すべき100周年記念の5年計画の始まりとして考えると、スワミからの奨励の様な気がします。
1月の終わりの夢で中学校時代に極めて仲が悪かった同級生が自分の家族として同居しているというものがありました。まだ道半ばですが自分の中で何かの浄化があったように思います。
------------------------------------------
神様を感謝の念と共に想起することを目標に過ごしてみました。
まだ感謝はしていませんが、嫌な気持ちは無くなったと思います。
色々とスワミのみ言葉を呼んだり聞いたりしていたからか、神様は必要不可欠という気持ちになってきたからだと思います。
嫌な気持ちが無くなったので、やってみてよかったなぁ、と思います。ありがとうございます
|